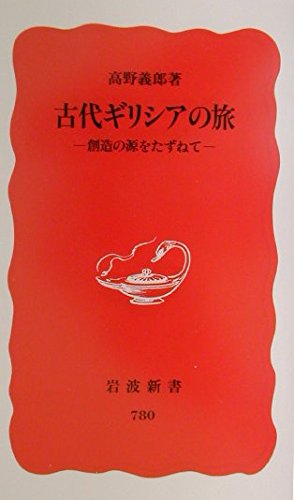高野義郎著「古代ギリシアの旅:創造の源をたずねて」
で著者は、ピュータゴラースが居を定めた3つの都市の全てに女神ヘーラーの大規模な神殿があった、と指摘しています。その3つの都市とは、ピュータゴラースが生まれた都市であるサモスと、後になって移住した南イタリアのクロトーン(現代名クロトーネ)と、そこからまた移住したメタポンティオン(現代名ベルナルダ)のことです。下にこれらの都市の位置を示します。
そして高野義郎氏は、ピュータゴラースと女神ヘーラーの間に何か関係があるのではないか、と考察を進めています。
直角三角形についての三平方の定理で知られるピタゴラス、正しくはピュータゴラースは、紀元前571年頃、サモスに生まれ、東方先進諸国に遊んで、前532年頃にクロトーンへ渡り、20年ほどしてメタポンティオンへ移り、その地で前497年頃に亡くなったと考えられています。
サモスは、最近はピタゴリオンと呼ばれていますが、アナトリアーに近いエーゲ海の島、サモス島の当時の首都でした。クロトーンとメタポンティオンとは、現在の南イタリアにあって、ともにイーオニア海(ギリシア語ではイーオニアー)に面しています。そして、これら三つの古代ギリシア人の都市には、そのいずれにも、女神ヘーラーに捧げられた神殿ヘーライオンの壮麗な建物がそびえていたのです。これはたんなる偶然にしか過ぎないのでしょうか。それとも、女神ヘーラー信仰は、ピュータゴラースの生涯やその思想に、本質的なかかわりをもっていたのでしょうか。
文中、「イーオニア海」という言葉が混乱を招きそうなので、補足させて下さい。これは小アジアやその近くにある島々からなるイオーニア(サモスもイオーニアに属します)とは別の場所を指しています。どうも語源が異なるようです。イーオニア海はイタリア半島とギリシアに挟まれた海域を指します。イーオニア海の北にあるのがアドリア海です。これで(些細な)補足を終えて、著者の考察に戻ります。
著者は、上記の3都市のヘーラー神殿の各部分の長さの比が同じであることに注目しています。そして、そこから1+2+3+4=10、という数字を導き出しています。
では、どのようにしてヘーラー神殿から、1,2,3,4が現れるのか、図で説明します。この図は神殿を上から見た図です。

一般にギリシアの神殿には内陣というものがあります。上の図での内側の長方形のことです。この内陣の間口の長さを1とすると、それ以外の部分の長さが2、3、4の比を持つ、というのが著者の主張です。これらの数の和が10になります。これはまさにピュータゴラースが神聖視していた数字です。著者は、ピュータゴラースが1+2+3+4=10を神聖視していたのは、ヘーラー信仰に由来すると推測しています。
 :
:
(メタポンティオンのヘーラー神殿の遺跡)
ところで、有名なアテネのパルテノン神殿にはこのような比はまったくありません。パルテノン神殿はヘーラーではなくアテーナーに捧げられた神殿です。著者は、上記の比はヘーラー神殿に特有のものである、と主張しています(もっとも、ヘーラー神殿であっても上記の比に従っていない神殿もあることを著者は認めています)。
それにしてもなぜ女神ヘーラーの数が10なのでしょうか? 著者はさまざまな理由を挙げていますが、その中で私が納得出来た理由は、妊娠の期間が10カ月ぐらいだから、というものです。ヘーラーは結婚や主婦の守り神でした。そして太古に遡れば地母神の性格を帯びていたと推測されます。母系制の社会と推測されるその時代には妊娠の期間が神聖視されたのは想像できます。そう考えると、地母神としての太古のヘーラーが10を聖数としていたのは、ありそうな話です。
私がこの説に興味を持つのは、ピュータゴラースの教説の2つの特徴、すなわち、「万物は数である」と主張するという特徴と「輪廻転生」を信じるという特徴の両方の由来を説明することが出来ると思うからです。ピュータゴラースの数へのこだわり、特に1+2+3+4=10という数字の重視は今までの記述で説明出来ます。一方、「輪廻転生」については、ヘーラー女神の本来的な神格が「死と再生を司る大地の女神」であると推定されることからヘーラー信仰には「輪廻転生」が自然に結びつくと思われ、その信仰内容をピュータゴラースが継承したと考えれば、説明出来るのではないかと思うのです。