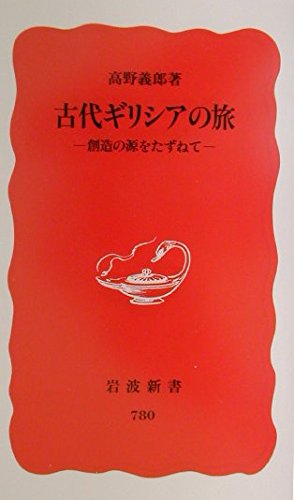女神ヘーラーが本来、どのような神格であったのかについて、高野義郎著「古代ギリシアの旅:創造の源をたずねて」
が、示唆に富む説明をしています。古代ギリシア人の世界――ヘラスと彼らは呼んでいました――をめぐった者なら誰も、女神ヘーラーに捧げられた壮麗な神殿の数々をながめて、その信仰のいかに広く、また、いかに深いものであったかをうかがい知ることができましょう。そして、いわゆるギリシア神話から来るこの女神のイメージとの大きな落差を感じるにちがいありません。

(イタリアのペストゥムに現存する巨大なヘーラー新神殿。全体像)
いわゆるギリシア神話では、ヘーラーは主神ゼウスの妃となっていますが、もともとは先住民族の神であったと考えられています。新しく侵入してきた民族の神ゼウスとの結婚は、両民族の融合を象徴したものといえましょう。(中略)古代ギリシアにおけるヘーラー信仰の中心地はアルゴスで、ヘーラーはこの地で主神として仰がれていたのでした。
それでは、ヘーラーはそもそもどのような女神であり、ヘーラー信仰とはどのようなものであったのでしょうか。それは明確ではないのですが、もともとは死を司る地下女神であり、入信者たちを死になじませる秘儀がおこなわれていたと推察されています。ヘーロドトスによれば、二人の孝行息子をもった母親が、人間として得られる最善のものを彼らに与えたまえと女神に祈ったところ、一夜を社(やしろ)の中で過ごした兄弟はふたたび目覚めることがなったというのです。
また、のちに述べるように、アルゴスの新神殿に祀られているヘーラー女神像は、ザクロを手にしていました。ザクロは多産と豊穣をあらわしています。ヘーラーの神格は、地下女神から、死と再生、多産と豊穣の地母神へと発展し、さらに、ゼウスと結ばれることによって、結婚の神となったのでしょう。
この著者は本職は理論物理学者だということですが、ギリシア、トルコ、イタリアにある古代ギリシアの遺跡をめぐり、文献もいろいろ目を通していて、この本の記述は手堅く、それでいてこの本の中には、普通の専門家が指摘しないような、はっとする仮定をいくつも書いています。
さて、上の引用に出てくる孝行息子の兄弟の話について、ヘーロドトスの「歴史」から原文をご紹介します。これはアテーナイの政治家にして賢者と呼ばれたソローンが、リュディア王クロイソスに、幸福な人間の例を話す、という設定になっています。さて、ソローンはこう述べたのでした。
それはクレオビスとビトンの兄弟でございましょう。二人はアルゴスの生れで、生活も不自由せず、その上体力に大層恵まれておりました。二人ともに体育競技に優勝しており、さらに次のような話が伝わっております。
アルゴスでヘラ女神の祭礼のあった折のこと、彼らの母親をどうしても牛車で社まで連れてゆかねばならぬことになりました。ところが牛が畑に出ていて時間に間に合いません。時間に追われ、二人の青年が牛代りに軛(くびき)に就いて車を曳き、母を載せて四十五スタディオンを走破して社へ着いたのでございます。祭礼に集まった群衆の環視の中でこの仕事を成し終えた兄弟は実に見事な大往生を遂げたのでございます。神様はこの実例をもって、人間にとっては生よりもむしろ死が願わしいものであることをはっきりとお示しになったのでございました。
すなわち、アルゴス人たちは彼らを囲んで、男たちは若者の体力を讃えますし、女たちは二人の母親に、何という良い息子を持たれたことかと祝福いたしました。母親は息子たちの奉仕と、二人の良い評判とをいたく喜んで、御神像の前に立って、かくも自分の名誉を揚げてくれた息子のクレオビスとビトンに、人間として得られる最善のものを与え給え、と女神に祈ったのでございます。この祈りの後、犠牲と饗宴の行事があり、若者は社の中で眠ったのでありますが、再び起き上ることはありませんでした。これが二人の最期だったのでございます。アルゴス人は二人を世にも優れた人物だとしてその立像を作らせ、デルポイへ奉納いたしたのでございます。
ヘロドトス著「歴史」巻1、30 から
残された母親の気持ちを考えるといたたまれなくなるのですが、ソローンはこの兄弟を幸福な人の例として挙げたのでした。
さて、この話の主題は「人間にとっては生よりもむしろ死が願わしい」という考えだと思います。もちろんこれは普通の考え方ではありません。この話がこう主張する背景には、独特の死生観があるのだろうと私は思います。
まず、あの世はこの世よりも優れてよい所だという考えがあるのだと思います。これについては、同じヘーロドトスがトラーキア人のトラウソイ族の習俗について書いていることが思い出されます。
トラウソイ族の風俗は、ほかのトラキア人と大体同じであるが、子供が生れたときと、人の死んだ時に、こんなことをする。子供が生れると、縁者のものがその子供のまわりに坐り、およそ人間の身に受ける不幸を全部数え上げ、この子供も生まれたからには、こうした数々の苦労に遭わなければならぬのだと、歎き悲しむのである。ところが死亡の場合には、死んだものは数々の憂き世の労苦を免れて、至福の境地に入ったのだというので、嬉々として笑い戯れながら土に埋めるのである。
ヘロドトス著「歴史」巻5、4 から
もうひとつは「生まれ変わり」または「輪廻」の信仰があったのではないか、と思います。大地の女神は、母なる女神であり、そこからあらゆるものが生まれ、また死して帰っていくところなのだと思います。そして死後の世界で(しばらくなのか、長い年月なのか分かりませんが)暮らしたのちに再びこの世に生をうける、と信じていたのではないのでしょうか?

太古にあっては生死を季節の移り変わりになぞらえて、循環的に捉えるほうが自然なような気がします。私はヘーラーの原初の姿を、「死を司る地下女神」ではなく「死と再生を司る大地の女神」と捉えたいと思います。私の中ではそれは「迷宮の女神」とつながっているような気がします。(「迷宮の女神」をめぐる私の思索を以前「ラビュリントイオ・ポトニア(迷宮の女主人)」に書きました。)